newsニュース
2025.7/14血糖値の動きは人によって変わる!今すぐ知りたいパターン別解説
2025年7月13日
『知らないと大損!血糖値の動きは人によって変わる!今すぐ知りたいパターン別解説』というテーマでライブが行われました!
その様子をスタッフ高代がレポートします。
血糖値を測ったことはことはありますか?リブレなどの機器を使ってご自分の血糖値のパターンを知ることができますが、そこまでしたことがある人は少ないかと思います。
今回は健康診断の採血データから推測するポイントなども教えていただきました。ぜひご自分のデータを確認してみてくださいね。食後にだるい、眠いなどの症状がある人は特に必見の情報です!

今日は血糖値のパターン別解説についてお話しします。
人によって血糖値の動き方が違い
継続的に血糖値を測ったことのある人は少ないと思いますが、皆さん、健康診断の採血で血糖値を測ったことはあると思います。
採血時は絶食状態で空腹時の血糖値を測ります。空腹時の血糖値の
70を切ると低血糖の診断になりますが、80台から症状が出る人
また、血糖値は緊張す
低血糖の症状がよくわからない人もいるかもしれま
<低血糖の症状>
- 食後に眠くなる。
- 空腹時にフラフラしたり手が震える人も。
- 甘いものがすごく食
べたくなる。 - 食欲を抑えられない。
- メンタル的に落ち込
みやすい。 - イライラしたり怒りっぽくなる。
- 緊張が強い。
- 汗をかきやすい。
- 手足が冷たい。
- 疲れやすい。
- 筋肉が付きにくい。
このような症状があると低血糖の可能性があります。
また、この時期は熱中症の症状と間違えてしまう人もいるので気を付けて
もう1つの採血で
これは2週間の血糖値の平均を表す項目で、糖尿病の診断に使われ
普通の血糖値が80台など低めで、HbA1cが5.5など、高めの人もいます。その場合は食後に高
そのため、採血の数値だけ
また、健康診断の数
太っているから高いとか、痩せているから低いとは限りません。痩
私が病院で指導していた頃は、明らかに肥満体型でも中性脂肪が高
中性脂肪は、糖質制限をしているとどうしても下がって
5
皆さん手元のデータで、血糖値、HbA1c、中性脂肪をまず見て
さて、ここからパターン別のお話をします。
血糖値をリブレな
食後に高血糖を起こして、その後一気に下がります。ジェットコー
この状態の人はインスリンがあまり効いていない人が多いです。
インスリンは血糖
そのような人はインスリンが効いていないので、血糖値を下げる機能が遅いんです
本来は血糖値の動きとしては、食後2時間ぐらいかけて90から1
こういう血糖値の人がいちばん多いですね。
これは糖尿病の予備軍のようなものです。糖に対して過剰反応をし
例えば、糖質制限をしていた人や、こまめにファスティングしてい
血糖値が一気に上がると、一気に下がるので、ちょっと糖質を
視聴者さんからコメント
・食後1、2時間後に不安感が出る
この時に出る不安感は、血糖値の影響であって、感情的なものではなく、性格ではないんです。
血糖値が急に下がっているから、不安
私も勉強を始めた頃は低血糖が酷かったので、イライラしたり、不
血糖値について学ぶと、食事で性格が変えられるのが分かります。
周りに不機嫌にキレる人がいたら、その人も
血糖値の乱高下があって、糖質制限をした経験がある人は、少しずつ糖質の量を増やして、少しずつ体を慣らしていくことが大事です。
食べ方によって血糖値の上がり方も変わるので、よく噛むことが大事です。それから、タンパク質を先に食べて、い
緊張が強い人の場合は、食事面だけでなく、メンタル面のケアが必要なことも
カウンセリングを受けた方がいい部分なんですけど、子供の頃から
そういう人はいくら食べ方を変えても血糖値が安定してきません。
ときどき、食べても食べても血糖値が上がらないパターン
このパターンの人はよりメンタル面のアプローチが必要で、食事ケアだけではなかなか改善しないパターンの人です。
視聴者さんからコメント
・血糖コントロールしてるけど不
そういう方の場合はカ
視聴者さんからコメント
・1日
食事に気を付けることに疲れてたら意味がないので、食事の時に意
料理ってすごくエネルギーを使う行為です。刃物を使うし、
添加物も気にしていい段
******
本日の内容は以上です!
血糖値の乱れがありそうだけど、ちゃんと測ったことがないからよくわからない…という人が多いのではないでしょうか?そのような方は過去に受けた健康診断の数値が本日紹介された数値の範囲かどうか確認してみましょう。
血糖値 / 80~100
HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)/ 5前後
中性脂肪 / 80~100
血糖値を上げにくくするために、よく噛んで食べる、適量の糖質(握りこぶし一個分の米)、タンパク質から食べるなどのコツをご紹介いただきました!
昔から緊張が強いなと感じる人は食事のケアだけでなく、カウンセリング検討しましょうね。
ぜひ、頑張りすぎない範囲で食事を改善してきましょうね。
******
血糖コントロールチャレンジ企画開催決定!
来週以降、みんなで血糖コントロールを行う企画をスタートします!
詳細は公式LINEでご案内します!
ご興味のある人はぜひ公式LINEにお入りください。
******
新しくYouTubeを開設しました!
低血糖をわかりやすく解説しています。
これからもどんどん動画をUPしますので、
ぜひチャンネル登録&高評価よろしくお願いします!
YouTubeで動
動画の最後のキーワードを公式LINEに送っていただくと、
プレゼントが届くよう
▼YouTubeはこちら▼
*****

7月31日(木)に
「子どもの集中力が上がる血糖コントロール」が
札幌で開催されます!
血糖値に配慮したお菓子屋さんの
藤井千晶さんと共同セミナーです。
高校生までのお子さんとご一緒にご参加ください。
お問い合わせは公式LINEへ。
*****
岡城美雪2冊目の著書が2024年9月26日に発売されました!
『「なんだかつらい…」がなくなる かくれ低血糖との付き合い方』
Amazonや、お近くの書店でお求めください!
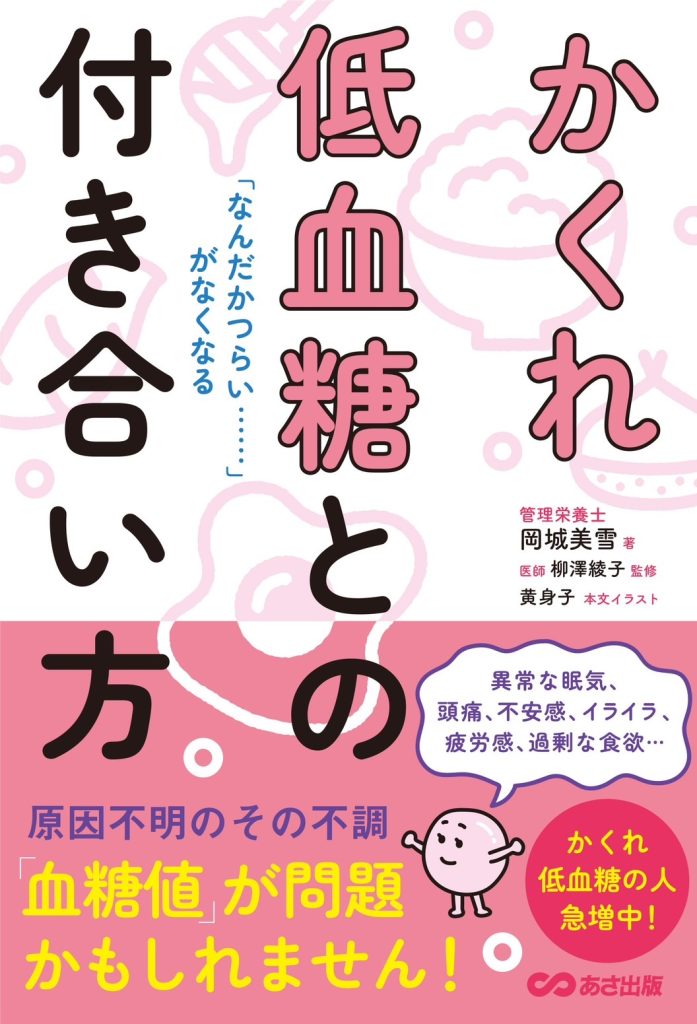
*
岡城美雪のライブは毎週日曜21時~Facebookやインスタで開催しています。
アーカイブはFacebookのオンラインサロンMyWellnessに一カ月間残っています。
