newsニュース
2025.10/05血糖コントロールの効果をなくす もったいないポイント5選
2025年10月5日
『栄養の効果が出ない? 血糖コントロールの効果をなくす もったいないポイント5選』というテーマでライブが行われました!
その様子をスタッフ高代がレポートします。
10月に入り、だいぶ涼しくなってきたものの、北海道育ちのみゆきさんにはまだまだ暑くて、まだ当分半袖を着ている予定、とのことでした!皆さんはいかがですか?お住いの地域にもよりますが、急に冷え込んだりもするので、お気をつけくださいね。
さて、本日は、血糖コントロールに取り組んでも効果をなくしてまうポイントについてのお話でした。せっかく血糖コントロールに取り組んでいるのに効果が出ない、とお悩みではないですか?今日のポイントを見直すと、良い方向へ動き出すかもしれません。多くの方に知ってもらいたい内容です!

今日は「血糖コントロールの効果をなくすもったいないポイント5選」というテーマでお話をしていきたいと思います。
私のところに来られる方の中には、がんばっているのに結果が出ないという方が本当に多いです。
食事も気をつけているし、運動もしているし、糖質もかなり意識して控えている。
それなのに血糖値がなかなか下がらない、体が軽くならない、疲れが取れない。
そういうご相談をよくいただきます。
でも実際に詳しくお話を聞いていくと、努力の方向が少し違っていることが多いんですね。
つまり「やっていること自体は間違っていないけれど、順番や重点がズレている」。
そのせいで、せっかくの努力がうまく反映されていないというケースです。
今日は、そうした“もったいないポイント”を5つに分けてお伝えしていきます。
どれもよくあることですし、どれか一つでも整うと結果が大きく変わるので、ぜひ一緒に確認していきましょう。
①方向性が間違っている
まず一つ目のポイントは、「方向性がズレていること」です。
これは本当に多いです。
たとえば「糖質をとにかく減らせば血糖値が下がる」と思って、必要以上に制限してしまう方がいます。
最初のうちは確かに数値が下がります。
でもそのあと、体がどんどん省エネモードになって代謝が落ちていく。
筋肉量も減って、燃やす力が弱くなる。
そうすると、同じ食事をしても血糖が上がりやすくなってしまいます。
つまり、一時的に良く見えるけれど、長期的には逆効果になるということです。
「糖質制限」「断食」「グルテンフリー」「カロリー制限」など、いろいろな方法がありますが、
どれも“合う人には合う”けれど、“誰にでも合う”わけではありません。
この“自分に合うかどうか”を見極めないまま始めてしまうと、
最初は良くてもどこかで壁がきます。
そこから頑張りすぎてしまって、さらに体調を崩す方も多いです。
もう一つ多いのは、「食事だけでなんとかしよう」としているケースです。
血糖コントロールというのは、食事だけの問題ではありません。
実際には、腸・自律神経・炎症・ホルモン・睡眠・感情など、
いろんな要素が関係しています。
つまり、食事の努力をしていても、他の部分でバランスが崩れていたら結果が出にくいんですね。
体は全体でひとつのシステムなので、どこかが滞っていると、
食事の改善もその力を十分に発揮できません。
私が見てきた中で、特に多いのは、
「ストレスで眠りが浅い」「朝の血糖値が高い」「夕方になるとだるい」
というパターンです。
こういう場合、食事内容をどんなに整えても、自律神経やホルモンバランスが乱れているために、
体が“血糖を安定させるスイッチ”を押せていないんですね。
だから、方向性を間違えると、がんばっているのに体が追いついてこないという状態になります。
血糖コントロールの効果を出している人たちは、
「食事」「腸」「自律神経」「炎症」「心理(心の状態)」、この5つを全体で見ています。
そして、「今の自分にはどこを整えるのが優先なのか」を判断しています。
この見極めができると、同じ努力でも結果が変わってきます。
努力が間違っているわけではなく、向かう方向がずれているだけなんです。
方向が整うと、体は必ず応えてくれます。
なぜこの“方向のズレ”が起きるかというと、
情報が多すぎるからです。
SNSや本などには、たくさんの「正しい方法」が載っています。
でも、「正しい方法」と「自分に合った方法」は別ものです。
だから私はいつも、「人の正解を自分の正解にしないでください」とお伝えしています。
大事なのは、自分の体を見て、体の声を聞いて、調整していくこと。
これが血糖コントロールを長く続ける上で一番大切な視点です。
②腸の状態が整っていない
次に多いのが、「腸の状態が整っていない」ことです。
腸は食べたものを吸収する場所であり、
ホルモンや神経伝達物質をつくる場所でもあります。
つまり、腸が乱れていると、どんなに良い食事をしてもその栄養が活かされにくくなる。
これは本当に多いパターンです。
たとえば、食事をすると腸から「GLP-1(ジーエルピー・ワン)」というホルモンが出ます。
このホルモンは血糖値を下げるインスリンの働きをサポートしてくれるものです。
でも、腸内環境が乱れていると、このGLP-1の分泌がうまくいかなくなります。
すると、同じ食事をしても血糖値が上がりやすくなる。
つまり、腸のコンディションが悪いだけで、努力が結果に反映されにくくなるということです。
腸内環境が悪くなる原因はいくつかあります。
たとえば、
-
ストレスや緊張で腸が硬くなっている
-
睡眠不足で腸のリズムが乱れている
-
食事の中に炎症を起こすもの(酸化油・添加物など)が多い
-
便秘や下痢を繰り返している
-
抗生物質やピルを長期間使っている
こういった要因が積み重なると、腸の粘膜が傷つき、
「栄養をきちんと吸収できない状態」になってしまいます。
腸の状態を整えただけで血糖値が安定する方はたくさんいます。
ある方は、3年以上朝の血糖値が下がらなかったのに、
腸のケアを始めた途端に数値が下がり、体調も軽くなりました。
食事内容はほとんど同じです。
変えたのは「腸のコンディションを整えること」だけ。
それくらい、腸の影響は大きいんです。
腸を整えるために大事なのは、特別なサプリや食品よりも、
まず「腸を緊張させない生活」をすることです。
早食い、ながら食べ、イライラしながらの食事。
これだけで腸の動きは鈍くなります。
逆に、ゆっくり噛んで、落ち着いて食べるだけでも、腸はちゃんと動き出します。
そして、腸のケアで意識してほしいのはこの3つです。
-
よく噛む
→ 消化酵素がしっかり出て腸の負担が減ります。 -
発酵食品をとる
→ 腸内細菌のバランスを整え、炎症を抑えます。 -
冷たいものを摂りすぎない
→ 冷えは腸の動きを止めます。
特別なことをしなくても、これだけで腸の働きはかなり変わります。
腸は体の中で一番外界に近い臓器です。
外からの影響(ストレス・食べ方・睡眠)を受けやすい場所でもあります。
だからこそ、腸を整えることが血糖コントロールの土台になります。
腸が整うと、食事の改善がスムーズに反映され、
エネルギーの流れも安定してきます。
結果、血糖値が自然に落ち着く方向に動き出す。
「最近結果が出にくいな」と感じたら、
まず腸のコンディションを見直してみてください。
③自律神経のバランスが乱れている
次に大事なポイントは、自律神経の緊張です。
血糖コントロールをする上で、体の緊張状態というのは、実は非常に大きな影響を与えます。
自律神経が乱れていると、どんなに食事に気をつけても、血糖値は安定しにくくなります。
具体的には、低血糖を頻繁に起こす方や、常に緊張している方は、胃腸の動きも悪くなり、消化吸収力が落ちます。
そのため、せっかく栄養を摂っても、体に十分に吸収されないことがあるんです。この無意識の緊張は、子どもの頃の経験や思考の癖が関係していることも多いです。
たとえば、叱られることや注意されることを敵だと認識してしまう思考の癖。これが大人になっても残っていると、体は常に緊張状態になり、自律神経のバランスが崩れます。
その結果、胃腸の働きが悪くなったり、血糖値が乱れやすくなったりするわけです。
なので、食事やサプリだけに頼るのではなく、心理的なアプローチ、カウンセリングなども重要になってきます。
自分の思考や体の緊張に気づき、根本から整えていくことが、血糖コントロールの成功には欠かせません。
④体の中の炎症が残っている
次のポイントは、体内の炎症です。これも血糖コントロールに大きな影響を与えます。
炎症があると、血糖値を上げるコルチゾールというホルモンが多く使われ、低血糖になりやすくなったり、血糖値が安定しにくくなったりします。
炎症といっても、見た目でわかるものばかりではありません。
例えば、歯周病や虫歯、口内炎、上咽頭炎(喉の奥の炎症)など、目に見えにくい炎症が血糖値に影響することも多いです。
鼻水や口呼吸、いびきがある方は、炎症が隠れている可能性が高いので注意が必要です。
また、腸の炎症や脂肪肝なども血糖コントロールの妨げになります。
こうした炎症がある場合は、まず医療機関でしっかりと診てもらい、必要な治療やケアを行うことが重要です。
⑤潜在意識レベルで「治りたくない」
最後のポイントは、潜在意識です。本人は治りたいと思っていても、無意識レベルで「治りたくない」と思っている場合があります。
こういう方は、何をやっても変化が頭打ちになりやすいです。
たとえば、体調を崩して仕事を休んでいる方は、治ってしまうと仕事に復帰しなければならない、という心理が働くことがあります。
治った方が健康には良いのに、無意識に「治らない方が都合がいい」と思ってしまうわけです。
この場合、カウンセリングで深く原因を掘り下げ、なぜ治りたくないのか、仕事や生活の中でどんなストレスや不安があるのかを整理することが重要です。
こうした心理的なブロックが外れると、血糖コントロールも一気に改善に向かいやすくなります。
大事なのは、体も心も含めて全体を見て改善していくことです。
食事だけに頼らず、心理面や生活習慣、腸内環境、炎症のケアまで幅広く整えることが、効果を最大化する近道になります。
******
本日の内容は以上です。
まとめ:「血糖コントロールの効果をなくすもったいない5つのポイント」
ここまででお話しした5つのポイントを整理すると次の通りです。
-
方向性が間違っている
→自分に合わない方法では効果が出にくい -
腸内環境が悪い
→消化吸収がうまくいかず、栄養が体に届かない -
自律神経の緊張が強い
→体が常に緊張して血糖値が安定しにくい -
体の中の炎症が残っている
→炎症によってホルモンバランスが乱れ、低血糖や血糖の乱高下が起こる -
潜在意識レベルで治りたくない
→無意識に改善を拒否してしまう心理的なブロック
この5つのどれかに当てはまると、せっかく努力しても血糖コントロールの効果が出にくくなります。ぜひ見直してみてくださいね。
今日のライブではMMC受講生の方から、変化を実感したというコメントをいただきました!
・みゆき先生に出会った直後は、やみくもにやってて成果得られなかったけど、個人セッションを受けたり、MMCに入って色々学んでから変わることができました。やっぱり学ぶって大事ですね。
・MMCに入って私は半年で変わった気がします。1年でやっとルーティンができてきました。で、2年以上経ってやっと思考の癖が変わりました。もう少し高めを目指していきたいです。
MMCでは期間内に無制限でみゆき先生のサポートが受けられます。健康診断の結果や、食事内容など、ご希望であればいくらでも見てもらえます!ご興味のある方は、公式LINE等で次期の募集開始情報をお待ちください。
スタッフ高代
*****
講師業やカウンセリング業に興味のある方必見!
MMCプロフェッショナルプレスクール開催決定!
12月に開講するMMCプロフェッショナルを少し早く体験できます。
なんと、無料です!来週以降、有料化の予定!お早めに!
ご興味のある方は公式LINEからお申込みできますので、ぜひご登録ください!

*****
岡城美雪のYouTubeでは、低血糖をわかりやすく解説しています。
ぜひチャンネル登録&高評価よろしくお願いします!
YouTubeで動
動画の最後のキーワードを公式LINEに送っていただくと、
プレゼントが届くよう
▼YouTubeはこちら▼
*****
岡城美雪2冊目の著書が2024年9月26日に発売されました!
『「なんだかつらい…」がなくなる かくれ低血糖との付き合い方』
Amazonや、お近くの書店でお求めください!
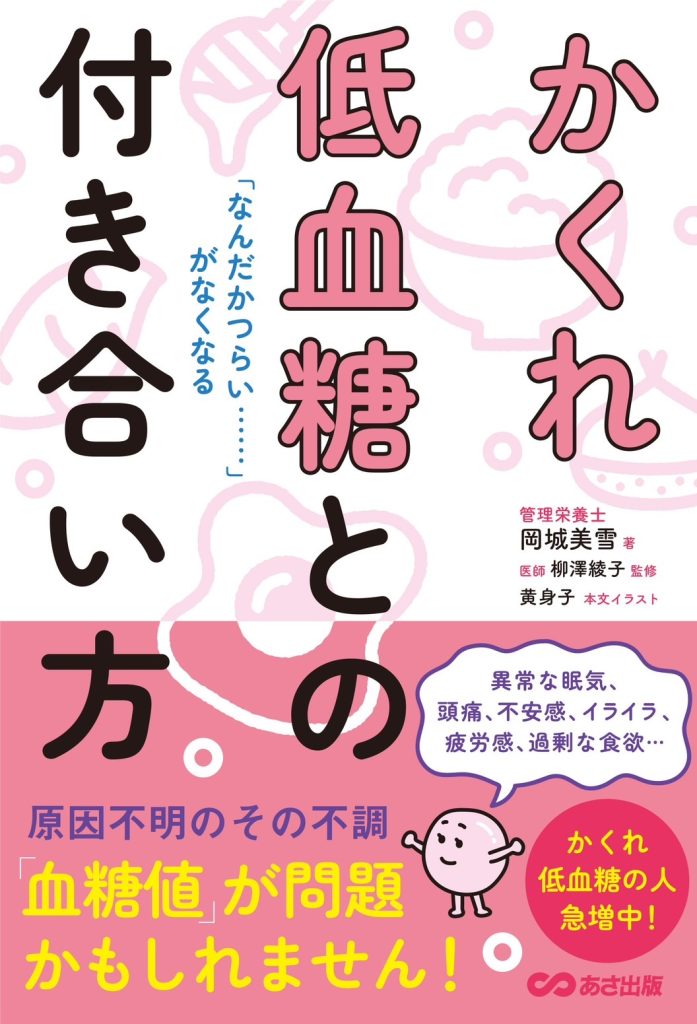
*
岡城美雪のライブは毎週日曜21時~YouTubeやインスタで開催しています。
