newsニュース
2025.3/17豪華ゲストによる子育て論!子供の自立心を養うには?
2025年3月16日
みゆきさんの出身大学の菅洋子教授をゲストにお呼びして、子育てについて熱く語りました!
菅洋子教授は、大学教授職のほかにジムの経営もされています。
シングルマザーでお子さんを2人育てたパワフルな方です。
この日の対談では、とても興味深い子育て論が展開されました!
子育てに悩んでいる人も、これから子供が欲しい人も、必見の内容です!

岡城:今日ご紹介する菅先生は、私と同じ管理栄養士で、大学教授もして、起業もされています。先生と話していて育児の話題になったとき、子育て論があまりに面白くて、コラボライブをお願いして、実現することができました。
菅:普段はみゆきさんが卒業した関東学院大学の栄養学部で教員をしています。1年ちょっと前から、デイサービスとパーソナルジムを経営しています。
岡城:先生とは10年以上のお付き合いになるんですけど、先日お話したときに、世のお母さんたちに聞いてほしいなと思うような面白い話をしていて。
菅:息子は今不動産会社で働いていて、娘は大学を中退して、美容系の専門学校に通っています。
岡城:先生はシングルマザーだったんですよね?
菅:そうです。結婚していたときも単身赴任が長かったので、育児に関してはいわゆるワンオペでした。それ自体は当たり前で、一人で育児するのが大変だとかはあまり思ったことがないです。むしろ、結婚していたときに相手に色々合わせたり、色々言われたり、ということの方がよほど大変だったので、離婚して自分で采配を振れるようになってからの方が気持ち的にはすごく楽だったと思います。
離婚したのは息子が小学校に上がって、娘が年中になる年でした。そのときはすごく忙しいベンチャー企業で働いていたんですよ。すごくやりがいがあって楽しかったんですけど、市の保育園が朝は7時半から、夜は7時までなので、24時間営業の託児所も活用していました。そこは市の保育園ではないので、どんな理由でも預かってくれます。飲み会でべろべろになって迎えに行っても、気持ちよく対応してくれる。市の保育園は働いている間しか預からないということになっているので、迎えに行く前に夕飯の買い物をしてはダメとか言われてしまいます。お金はかかったけど、民間の託児所にはほんとうに助けてもらったと思ってますね。
親が一人になると、子供はこの親についていくしかないので、嫌ならついてこなくて結構、みたいな雰囲気が漂っているから、子供も多分、小さいながらに腹をくくっていたという感じですね。仕事は本当に忙しくて、一年のうち、包丁を持って料理したのは何日だろう、というくらい。
そのころのことを子供に聞くと、あの頃はひどかったとは言わないんですよね。もう、そんなもんなのだ、と。お母さんはすごく頑張って働いているな、というのが伝わっていたので、文句を言われたり、というのもなかったですね。
岡城:そのとき先生はどうやって仕事と育児のバランスを取ったり、自分の健康管理をしていたんですか?
菅:バランスなんて考えてませんでしたね。仕事の合間にやらなくてはいけないことをやる、みたいな。授業参観なんかも、絶対行かなきゃと思わなかったし、下の子は来てほしい感じだったので、とりあえず終わりごろ行って、来ましたよ~と手を振ってアピールしたりとか。
運動会は、上の子は運動神経が良かったので、私も見たかったので行ってたけど、下の子は運動神経は良くなかったけど、来て欲しいというので、一応ビデオを持って行って。バランスを取っていたと言えば、それぐらいかな。
仕事は子供に何かあるからと言って休める状況じゃなかったので、そんなもんだと思って私はやっていたし、子供もそんなもんだと思っていたと思うんですよね。
岡城:世のお母さんたちは、子供のためにやろうという気持ちが強い人が結構いると思うけど、先生はどう思いますか?
菅:やりたい人はやればいいと思うんですよね。子供が小さいうちはできるだけ家にいてあげたいとか、それって子供がそうして欲しいというより、親がそうしたいという気持ちが強いと思うので。だからそうしたい気持ちがあって、そうできるなら、やればいいと思うんですよ。
私はそうできる余裕もなかったし、性格的に淡泊で、そもそもしたいとも思わなかったです。私の両親は高校の教員で忙しくて、母親も修学旅行で何日かいないとか、そういうことが普通にありました。お買い物も小学校低学年のうちからやっていました。毎日夜に母から電話がかかってきて、電話を受けると、ご飯2合炊いてとか、お風呂沸かしてとか頼まれます。それを兄とじゃんけんで分担していました。それが当たり前でした。
別にすごく丁寧に手をかけてやるということ自体が悪いことだとは思わないです。ただ、自分で自分の決まり事をたくさん作って、あれもこれもやるために自分のことを置いておく、となると、子育てのために自分が我慢している気持ちになると思うんです。
私は仲良い友人からは、子供を放置しすぎじゃないかとか、散々言われてきました。でも今は、それなりに子供が育って、良い子だって周りは言ってくれるんですけどね。
基本的には放置というか、放牧だったんですが、ハメを外しそうになったら、もちろん色々言ったりとかはありました。私の中での基準はあったので、そのときには口うるさく言っていました。
岡城:どんな基準だったんですか?
菅:例えば、お金の使い方とか、連絡をすることとか、お礼を言うとか、陰口をたたかないとかですね。部活の指導者の文句とかは本当に良くないことだよって厳しく言ってました。
礼儀については、息子は寮に入っていたので、現地の同級生の親御さんに色々お世話になっていて。そういうときは私も親としてお礼を言いたいと思っているのに、息子はお世話になったことを報告しないことがあって。だから誰かに何かをしてもらったら、必ず報告するように、と。
岡城:お子さんが寮に入ることに、心配は特になかったですか?
菅:むしろ、高校選びの条件が絶対に寮があるところでした。横浜市って、公立高校に給食がないんですよ。今はハマ弁がありますが、中学校も給食がなかったから、中学校に通っていた時は毎日お弁当を作っていたんです。3年間お弁当を作るのって大変でした。これから高校になったら朝も早いし、遠征があったり、それでお弁当を作っていたら私の生活が侵害されるんじゃないかと。世の中のちゃんとやってるお母さんには申し訳ないですけれども。
それに、私自身も高校は寮生活だったので、高校生くらいのタイミングで親元を離れるのは自立のために良いと私自身も思っていたのです。
息子には、高校で野球を続けるなら絶対に寮があるところと洗脳していたので、本人もそういうつもりでいました。本人も寮で色々な経験ができたので、良かったんじゃないかと思います。
岡城:娘さんも中学からお弁当が始まったけど、作ってなかったんですよね?
菅:娘は息子と3歳違いなので、息子を寮に入れたら、入れ違いで中学生になったんです。「ママはもうお兄ちゃんで疲れたから、しばらくママ業廃業するから、お弁当自分で作ってね」と言って、数日放置したんですよね。そうしたら、残り物やご飯をタッパーに詰めて持って行って、ほとんど料理したことないので、真っ黒焦げの卵焼きを作ったりとかして。それでも放置してたら、だんだん作れるようになってきました。だから中学~高校の6年間で私が娘にお弁当を作ったのって多分5回もないと思います。
岡城:娘さんがあまりお弁当が作れてなかったときも手を出さなかったんですか?
菅:手を出さなかったですね。自分で作らないと食べられないからちゃんと作ってたし。本人も主婦目線で夕飯の残り物を詰めたりしてましたから。娘は高校で剣道をやってて、お小遣いはたくさん買い食いできるほどあげてなかったから、お弁当も大きいタッパーでたくさん作っていました。
大学になって息子が家に戻ってきたとき、息子はプロ野球を目指していたので、トレーナー目線で栄養管理のために息子のお弁当は作っていました。その傍らで娘は自分のお弁当を作っていました。中学校3年間で弁当作りをやれるようになってたから、それがすごく良かったと思って、中途半端に私が手を差し伸べるよりいいなと思いました。
息子はスポーツもできるし勉強もそこそこできますが、娘はのんびりしている性格だったので、息子は褒められ、娘はけなされ、という構図ができていました。でもお弁当作りに関しては自信になっていたと思います。娘がお弁当を作れるというのが私の自慢でもありました。
岡城:子供が中学生、高校生になってもなかなか手を離せないというお母さんいますよね。そういう方にアドバイスをするとしたらどうでしょうか。
菅:子育ては、究極の目標は子の自立だと思うんですよ。だから何がいちばん子の自立に繋がるかなということをよく考えていました。私は子にやってあげられないことが多くて、周りはかわいそうだという人もいたかもしれないけど、私はそう思ってなくて、子の自立を思えば、子ができることは子がやった方が良いと思うので、親がやってあげたいという気持ちよりも子供の成長にとっていいのは何かな、というのを考えて、あえてやらない、我慢することも必要じゃないかと思います。
岡城:子の自立が大事という意識が常にあったんですね。
菅:そうですね。学生が終わったら、近くに就職したとしても、家を出てねと言ってます。息子は最初家にいようかなと言ってたんですか、家にいるなら15万円入れてと言ったら出ていきました。私としても就職した子が家にいると、今日は仕事なのか、とか、帰って来ないとか、そういうことが気になったりするので、そういうのが嫌なんです。離れていると一切気にならない。
息子と離れて暮らしていても、元気なの?最近どうなの?というようなLINEはしたことがありません。ただ、勉強は大事だと伝えていたので、定期テストの前には、頑張りなと送っていました。
岡城:息子さんは学年トップ3をキープしていたんですよね。
菅:野球の強豪校で、普通の進学校とは違いますが、ただ、どんなところでも、ちゃんと授業を聞いて良い成績を収めるのは努力しないとできないことなので、その経験は今後も生きてくると思います。
岡城:息子さんも今はバリバリ稼いでいらっしゃいますよね。
菅:不動産会社に入って、野球をやりながら資格の勉強をしていました。仕事も大変で、営業の経験のない中、何とか乗り越えて頑張っているんですけど。
岡城:お母さんのスポンサーになりたいとも言っているんですよね。
菅:会社の業績もよく、十分な稼ぎはあるみたいです。自由に使えるお金が増えてきて、不安もあるようです。浪費したりとか。だったら有益なものにお金を使いたいということで、私もまだ会社を始めて1年半なので、何か助けられるのであれば、ということを言ってくれています。
岡城:お金の教育はどういうふうにしていましたか?
菅:ちゃんとしたお小遣いはあげてなくて、必要なものは買ってあげていた感じでした。ゲームや流行りものに関して、私の親はあまり買ってくれなくて、親を恨むようなこともあったけど、そのプアな状況の方が色々工夫したり、お友達に頭を下げて借りたりとかするようになります。何でもかんでも買ってもらうとありがたみもなくなります。その価値観があったので少し厳しめに制限はしていました。
あるとき娘が自由にやりくりしたいということで、いつもよりちょっと多い額を渡したんですよ。足りなくなってもお母さんは出さないからね、と言って。部活帰りに友達とバスに乗るときも、娘は家の前の坂道でバスに乗るためにそれを断って、学校から駅までは歩いて行ったりしていました。でもそういうことで愚痴を言われたことはないので、うまくやりくりしてたんじゃないかと思います。
岡城:すごいですね。友達に合わせたいってあると思うんですけど。
菅:娘は孤独に耐えられる強さがある気がします。孤独に耐えられる強さがある人って周りに対しても優しさを持てるんじゃないかなと思っていて、特に友達と折り合いが悪くて、ちょっと一人ぼっちなんていう時もあるかもしれないけど、例えば本を読んで一人の時間に没頭できるとかね。そうすると周りにどう思われてるとかあんまり気にしなくても過ごせることもできるから。私が放置していたからかもしれないけど、そういう一人遊びができる強さがあると思います。
岡城:ゲームとか、買ってなかったと言ってましたよね。
菅:これは私も親に買ってもらえなかったんです。友達の家に行って借りたりしてました。ただ、時間を浪費する中毒性があるということは気になってましたね。ゲームはなきゃないで、工夫して遊べますから。少なくとも小学校、中学校の時は買わないということにしていました。
岡城:お子さん二人とも、あまり人の目を気にしない感じですか?
菅:気にしないわけではないと思うけど、他の子よりは我が道を行くみたいなタイプかなと思います。
岡城:それはみんなが同じゲームをやってても、一人でやっていくとか、そういう環境の中で鍛えられた感じなんですか?
菅:娘も息子も中学校の1~2年のころは携帯を持たせてなかったので、ほとんど周りが携帯を持っていて、集合場所に行ったら集合時間場所が変わってて、みんながいなかったという経験を何回もしています。でも、そういうことがあるから事前に必ず誰かに確認しなって私はいつも言っていたので。その確認をせずに行って、結果的に変わってた。しょんぼりして帰ってきて、かわいそうにと思ったこともありました。
岡城:サバイバル能力というか、生き抜く力はつきますよね。娘さんのインスタを見てますが、すごい個性的ですよね。
菅:娘は私から見ても理解不能なタイプです。でもまあ、それもいいのかなと。本当はもっとこうしてあげればよかったと思うこともあります。娘にも「ママ、もうちょっと丁寧に育てればよかったと思ってるでしょ」って言われます。内心ちょっとは思ってます。
息子が就職して最初の1~2か月はお金に困っていて、ゴールデンウィークに初めて帰ってきたときに、娘に「お前、こういう家に住んでご飯食べられるのは当たり前じゃないんだぞ」って結構偉そうに言ってくれました。いいこと言うじゃん、と思ったんですけど、娘は、「お兄ちゃんはちやほやされて育ったからそういう風に思うんだよ」って言ってました。それも一理あると思いました。
岡城:お互いに兄妹ってそういうところありますよね。自分よりももう一人の兄妹の方が可愛がってもらえたように感じるのはあると思います。私も子供は放牧してると思うんですけど、お話をお聞きしたら放牧のレベルが違いすぎて。
菅:子供に対して心配しすぎないレベルが違うと思います。私の親が私に対してそうしてきたレベルくらいまでは当たり前だと思っていたので。当時は専業主婦が多かったので、雨が降れば傘が届くとか、おうちに帰れば手作りおやつがあるとか、そういう風に育った人はそういう風にしたいと思うのが普通かもしれない。うちはそういうことがなくて、それが当たり前でした。
やる気を出させるような上手な子育てしている人を見習うと、また違ったんじゃないかと思うけど、私は子供を乗せるためにうまく褒めるとかはあまりできなかったです。
放牧しても愛情をもって接すれば子供はうまく育ちます。私はママ友にも恵まれたし、仕事仲間にも恵まれたし、だから、子供に対してもそういう接し方ができたのかなという気がします。
自分に心のゆとりがないときは子供に八つ当たりしてしまうじゃないですか。それをあるとき気づいて、結局自分が精神衛生上すごくいい状態だと子供に対してもゆとりをもって接せられるというのはすごく思いました。でも、そうじゃないときも多かったし、そういうときは子供たちも分かっていたと思うんですよ。それをうまくかわす方法も覚えていたと思います。
岡城:先生自身がすごく仕事を一生懸命やってきたから、自分にとって大事なのは育児だけじゃなかったわけですよね。
菅:育休取った時は暇すぎて、毎日電気の検針までしてみたりとか。余計なことをやって時間をつぶしていた感じです。育休中よりも仕事しているときのほうがよかったです。やりたいことが色々あったから。それをやる傍ら育児をしていたという感じ。
岡城:先生が楽しそうに仕事をしている姿を、お子さんが見ていたんですね。
菅:子供のためを思って子育てした感覚はないのだけど、子育ての終わりに近づいてみると、子供がこんな私の背中を見ていてくれていたという感じはあります。子供は私に頼らずに生きていけるけど、子供が小さいうちは、3人で生活できるだけの収入を得る覚悟はありました。
岡城:自分は好きなことをやっていたけど、それができなくなっても、ちゃんとその分は稼ぐという意識はあったということなんですね。
菅:それはありましたね。身体も丈夫だったので、何でもできると思ってましたね。専門性がある仕事じゃなくても。マラソンも趣味の世界でありながら、運動生理学とかスポーツ栄養学も専門なので、マラソンに関して勉強してきたことを自分の体で体現して、色々感じたり試したりできるから、趣味と実益を兼ねてる感じですね。
岡城:私は栄養学に興味があって大学に入ったんですけど、授業もついていけないようなときに、先生の授業を受けたら、ランナーのパフォーマンス上げるにはこういう食事をするといいという話をしてくれてたので。それがすごく面白かったです。先生のおかげで大学が楽しくなりました。
菅:みゆきさんは忙しいのに毎年のようにゼミに顔を出してくれて、ここ数年は毎回ビジネスの話をして、私も楽しみです。
岡城:先生の話は面白くてわかりやすくて、こういう育児の講演もぜひして欲しいです。
菅:自分の育児論がどうのなんて考えたことなかったけど、今日話してみて、成り行き上そうしたというだけのことと、こだわってたこととか、いろいろ三段階くらいあるなと思いました。それがベストだったかはわからないけど、少なくともこだわってたことに関してはちゃんと子供に伝わってたと思います。
子供に聞いたら、もしかしたら、これが嫌だったとかあるかもしれないけど、そうしたら反面教師といういい言葉があるからね。親がこうだったから、自分は違うようにしようと思ってくれればいいと思うのでね。これから先、自立した後は自分で人生を切り開けばいいと思うので、これから先は子供に対して手助けする必要はないし、気にしない。
苦労も自分の糧になると思います。息子が就職してすぐ、お金に困ってお昼におにぎり握って持って行ってるって話を聞いて、良い経験してるねって心から思ったから。普通の親なら何か送ってあげるとかするかもしれないけど、私はそういう感覚が全くなかったです。
岡城:そろそろ60分経ちます。ありがとうございます。先生のマラソンの分析なども見ていると面白いので、ぜひ皆さん、見てみてください。
*****
本日の内容は以上です!
育児にこだわりすぎてしまう人、子供が思い通りにならないと悩んでいる人には大きなヒントがあったのではないでしょうか。親が好きなことを突き詰めても、その背中を見せることをでき、愛情をもって接すれば、子供はしっかりと育っていく、ということが伝わってきました。
悩んだら、「子供の自立のためにはどうすればいいのか?」…そう問いかけてみてくださいね。
***
新しくYouTubeを開設しました!
低血糖をわかりやすく解説しています。
これからもどんどん動画をUPしますので、
ぜひチャンネル登録&高評価よろしくお願いします!
▼YouTubeはこちら▼
*****
岡城美雪2冊目の著書が9月26日に発売されました!
『「なんだかつらい…」がなくなる かくれ低血糖との付き合い方』
Amazonや、お近くの書店でお求めください!
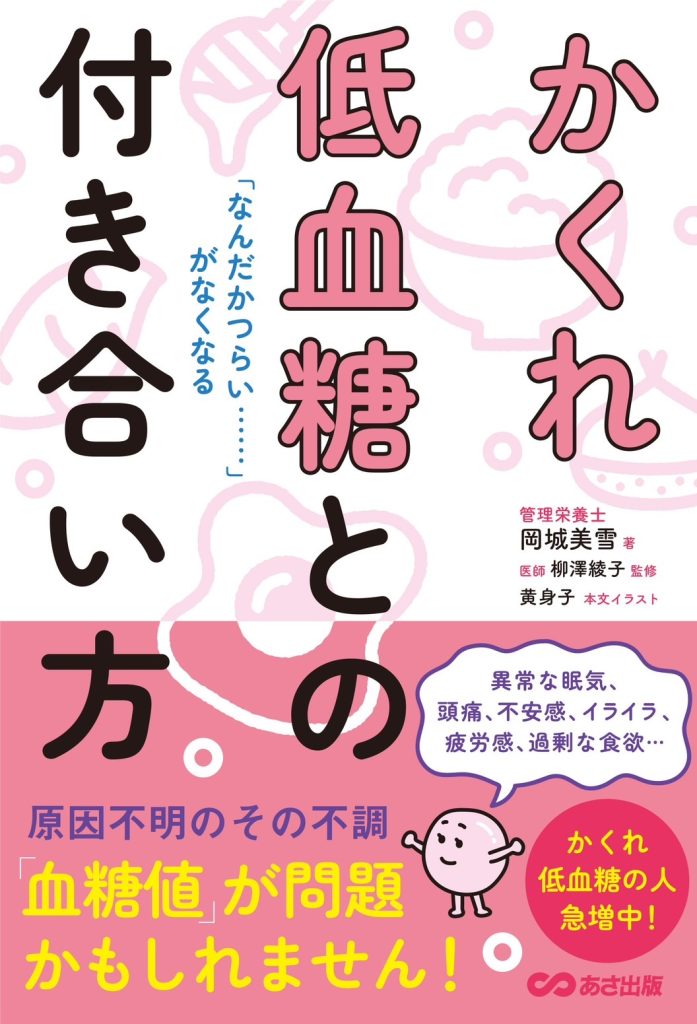
*
岡城美雪のライブは毎週日曜21時~Facebookやインスタで開催しています。
アーカイブはFacebookのオンラインサロンMyWellnessに一カ月間残っています。
